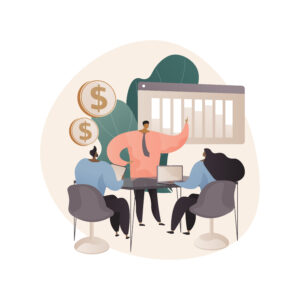【税務注意】定期同額給与の否認リスクとその回避策について
目次
Toggle 法人の役員報酬を損金に算入するためには、法人税法で定められた一定の要件を満たす必要があります。その中で最も一般的な方法が「定期同額給与」ですが、適切な運用を行わなければ、税務上その損金算入が否認されるリスクがあることをご存じでしょうか。
法人の役員報酬を損金に算入するためには、法人税法で定められた一定の要件を満たす必要があります。その中で最も一般的な方法が「定期同額給与」ですが、適切な運用を行わなければ、税務上その損金算入が否認されるリスクがあることをご存じでしょうか。
今回は、定期同額給与の基本的な仕組みと、否認される可能性のあるケース、さらにリスクを回避するための具体的な対策について解説いたします。
◆ 定期同額給与とは?
定期同額給与とは、法人が役員に支給する給与のうち、
- 1か月以下の一定の期間ごとに
- 同額の金額を
- 継続的に支給するもの
を指し、法人税法上、役員給与の中で最も一般的に損金算入が認められている方法です。
具体的には、たとえば「毎月25日に50万円を支払う」といった支給形態が該当します。
◆ 定期同額給与の「否認リスク」とは?
定期同額給与として適切に支給しているつもりでも、形式や実態が法令の要件を満たしていない場合、税務署により損金算入が否認されることがあります。
否認された場合、以下のような影響があります:
- 否認された給与部分が損金にできず、法人税額が増加
- 過去年度に遡って修正申告が必要
- 場合によっては過少申告加算税や延滞税が課される
◆ 否認される可能性がある主なケース
- 支給金額に変動がある
業績によって金額を増減させるなど、支給金額が月によって異なる場合は定期同額給与と認められません。業績が好調だからといって、自由に報酬額を変更することはできませんので、報酬額の決定は慎重に行いましょう。
対策: 年度の途中で報酬を変更する場合は、次に述べる「3ヶ月ルール」に注意が必要です。
- 期首から3ヶ月を超えて報酬を変更した
定期同額給与の金額は、原則として事業年度開始から3ヶ月以内に決定されたものでなければなりません。
例えば、事業年度が4月開始の場合、7月以降に報酬を変更すると、以降の支給は定期同額給与と認められない可能性があります。
対策: 報酬改定は、原則として事業年度開始から3ヶ月以内に行いましょう。
- 現物給与(社宅・車両など)の適切な処理がされていない
社宅や役員用車両など、現物で提供している給与相当分について、評価額の算出や処理が不適切な場合も否認対象となります。
対策: 税務上の取り扱いを確認し、適切に処理を行いましょう。
◆ 定期同額給与の運用で意識すべきこと
| 項目 | 対応のポイント |
|---|---|
| 支給金額 | 毎月同額にする |
| 報酬改定 | 期首から3ヶ月以内に行う |
| 手続書類 | 株主総会議事録・取締役会議事録などを整備 |
◆ まとめ
定期同額給与は、中小企業にとって非常に有効な損金算入手段ですが、その運用に少しでもミスがあると、税務上大きなリスクとなります。
特に、支給金額・支給日・報酬改定のタイミングには細心の注意が必要です。
定期同額給与の適正な運用を行うことで、税務リスクを未然に防ぎ、企業経営をより安定させることができます。
◆最後に
「毎月きちんと支払っているから大丈夫」と思っていても、思わぬところで否認されるのが定期同額給与の怖いところです。
少しの見落としが税務調査で大きな指摘につながるケースも少なくありません。
年度初めの報酬改定時期には、今一度手続きや金額設定を見直し、安心できる運用を心がけましょう。