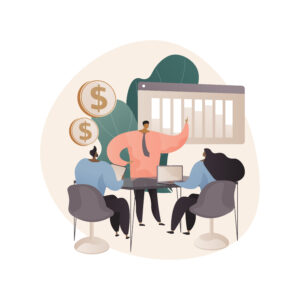法人成りのメリット・デメリット
目次
Toggle法人成り(個人事業主から法人への移行)は、事業規模の拡大や信用力の向上などに伴い、多くの事業者が検討する重要なステップです。ただし、法人化には明確なメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。
以下では、「法人成りのメリットとデメリット」について、税務・経営・社会的側面からご紹介します。

【一覧表】法人成りのメリット・デメリット
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 税務 | 所得分散による節税が可能経費計上の幅が広がる赤字の繰越が最大10年 | 税理士報酬など経理コストが増加、赤字でも地方税均等割りの納税が必ず発生 |
| 社会保険 | 社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できる | 社会保険料の負担が大きくなる(会社・役員双方) |
| 信用・取引 | 銀行・取引先からの信用力向上融資・契約が有利になるケースも | 登記情報が公開される(代表者の住所など) |
| 資産保護 | 会社と個人の資産が分離され、リスクが限定される | 法人の経理・資産管理が複雑になる |
| 事業承継 | 株式による事業承継が可能 | 運用には会社法や税法の知識が必要 |
メリットの詳細解説
- 節税の選択肢が広がる
- 役員報酬や給与の支払いにより、所得を分散させることができます(法人税と所得税の税率差を活用)。
- 退職金の積立も可能になり、将来の資金形成に有利です。
- 経費計上の幅が広くなる(出張費、社宅、福利厚生など)。
- 信用力の向上
- 法人化により、銀行融資や大手企業との取引の審査に通りやすくなる傾向があります。
- 名刺に「株式会社」や「合同会社」がつくだけで、社会的な信頼性が増す場合も。
- 事業承継・資産保全がしやすい
- 株式という形で事業を承継することが可能。
- 個人資産と法人資産を明確に分けることで、万が一のトラブル時にリスクを限定できる。
デメリットの詳細解説
- 維持コストがかかる
- 赤字でも法人住民税(均等割)が最低7万円(資本金や従業員数、また地域により異なる)発生。
- 決算や税務申告は複雑になるため、税理士などの専門家への依頼が必須となり、コストが増える。
- 社会保険の強制加入
- 役員1人だけでも法人の場合は、健康保険・厚生年金の加入が義務。
- 個人事業主時代より保険料の負担が増加するケースがほとんど。
- 自由度が下がる
- お金の使い方が制限される(会社の利益=個人の収入ではない)。
- 法人名義の資産は「会社のもの」であり、勝手に引き出すことはできない。
- 会計処理が厳格に求められ、帳簿・税務管理に手間がかかる。
法人成りを検討すべきタイミング
次のような状況が見られる場合、法人成りを前向きに検討する価値があります:
- 年間の所得が900万円以上
- 今後、人を雇用する予定がある
- 取引先から法人化を求められている
- 設備投資やインボイス対応が必要
- 節税や将来の事業承継を見据えている
まとめ:法人成りは目的を見極めて
法人成りは、「節税」「信用力」「資産の分離」など多くのメリットをもたらしますが、同時に「コスト」「手間」「制度上の制約」も生じます。
法人と個人でどちらが良いのか、年齢・家族構成・居住状況・生活費などにより大きく変わります。例えば、売上規模が1,500万円~2,000万円・40代独身・賃貸住まいの方の場合、個人事業主のままでも法人化しても、個人法人合わせた税金等(所得税・法人税・社会保険料)の負担はさほど変わりません。(法人化した場合の給与は月30万円と仮定)
最終的には、将来のビジョンに応じて、法人化の是非を慎重に検討することが重要です。
「法人化シミュレーション(税金・社会保険料の比較)」なども作成可能です。お気軽にご相談ください。
最後に:合わせて気をつけるべき事項を列挙します
- 設立・解散コスト
- 法人設立時には登録免許税や定款認証費用など初期費用が発生します。また、解散・清算時にも費用と手続きが必要です。
- 事業内容による許認可
- 法人化により新たに許認可が必要となる業種もあります。個人事業主時代と異なる規制が適用される場合があるため、事前確認が重要です。
- 役員報酬の決定と変更制限
- 役員報酬は原則として事業年度開始後3カ月以内に決定し、その後は原則として期中の変更ができません。柔軟な給与調整が難しくなります。
- 赤字繰越の適用要件
- 法人の赤字繰越(最長10年)は「青色申告」の承認を受けていることが前提です。承認を受けていない場合は適用できません。
- 消費税の免税期間
- 新設法人は原則として設立1期目・2期目は消費税が免除される場合がありますが、資本金や売上規模によっては初年度から課税事業者となるケースもあります。
- 社会保険の適用除外例
- 役員1名のみの法人でも、一定条件下で社会保険適用除外となる場合があります(例:家族経営の特例等)。必ずしも全ての法人が強制加入になるわけではありません。
繰り返しになりますが、法人化後は、会計・税務・社会保険・法務など多岐に渡る管理体制が必要となります。専門家への相談やシミュレーションを活用し、総合的に判断してください。